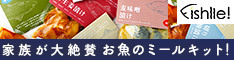はじめに:この読みものについて
このページでは、ブログのテーマである「サメの保全」と「わたしたちの社会との関係性」について、背景や視点を深堀りしています。
専門的な話題も含まれますが、決して「環境活動家だけのもの」ではなく、「なぜサメなの?」「海と自分にどんな関係があるの?」と問いを持った方に向けて綴っています。
サメの保全とそのむずかしさ
IUCN(国際自然保護連合)のレッドリストによると、世界のサメ類の31%(167種)が絶滅危惧種に指定されています。

サメたちが追い詰められている背景には、乱獲、フカヒレ目的の漁獲、気候変動による海洋環境の変化、プラスチック汚染など、わたしたち人間の活動があります。
サメ映画やメディアによって作られた「恐ろしい捕食者」というイメージも、保全の妨げになる要素です。

日本においては、「フカヒレ産業の維持」と「サメの保護」がしばしば対立軸として語られます。ですが、わたしはその二項対立を超えて、「サメがいるからこそ産業も未来も成り立つ」という道を探りたいと思っています。
サメの保全=自然保護ではなく、「未来の暮らしの設計」なのです。
サメと環境問題のつながり
サメの保全は、「環境問題」を「自分ごと」として考えるための入り口でもあります。
海洋酸性化、マイクロプラスチック、異常気象──すべての環境問題は、サメたちの未来に直結しています。
実は、海も気候変動による変化を避けることはできません。
そのため、海で暮らすサメたちの生態や生息環境にも、大きな影響が出てきています。
他人事ではない海のこと
「サメや海と、わたしの暮らしって本当に関係あるの?」
そう感じるのも、無理はないと思います。
けれど──
気候変動の影響は、すでにわたしたちの日常にも届いています。
たとえば、
- ゲリラ豪雨や猛暑があたりまえになってきたこと
- 四季の感覚がなんとなくズレてきたと感じること
- 毎年のように巨大台風がくること
こうした変化のひとつひとつが、じつは「気候と海のつながり」を物語っています。
そして、その海の中で生きているサメたちにも、同じように影響が広がっているのです。


海の変化は、わたしたちの暮らしからはなかなか見えにくいものです。
でももし、その変化に気がつくことがあればもう手遅れなのかもしれません。
南オーストラリアでホホジロザメの打ち上げが続発
2025年4月後半から5月初頭にかけて、南オーストラリアの複数のビーチで、
体長3メートル級のホホジロザメが次々と浅瀬に打ち上げられるという異常事態が起きました。
原因として疑われているのが、有毒な藍藻(アオコ)の大量発生です。
藍藻は、海の酸素濃度を急激に下げたり、神経系に影響を与えたりすることがあり、
エイや他の魚類でも異常行動や打ち上げが報告されるなど、生態系全体への深刻なダメージが懸念されています。
背景にあるのは、気候変動、海洋汚染、そして農地から流れ出す栄養塩による「富栄養化」。
これは、わたしたち人間の暮らしが引き起こした、複合的な「海の異変」なのかもしれません。

サメの魅力と楽しさ
サメは「怖い存在」ではなく、知れば知るほど面白い生きものです。
- 感覚器官の進化
- さまざまな種の保存の戦略
- 種によって全く異なる性質や生活環境
こうした知識を知ることは、サメへの偏見を取り除くだけでなく、生態系におけるサメの役割を見直すきっかけにもなります。
わたしは研究者ではありませんが、サメの「となりで暮らすひと」として、好きだからこそ発信を続けています。
このブログでは、サメの生態や行動学の豆知識、水族館の観察記、哲学的な考察なども含めて、サメの面白さを伝えています。

わたしのブログの始まりと、にゃぶりの存在
2006年、初めて書いたサメブログは、えのすいのタッチプールの話と「フカヒレを食べていいのか」の葛藤でした。
あれから17年以上、いろんな学びを経て今のブログがあります。
相棒はホホジロザメの女の子「にゃぶり」。
いつもわたしの隣で、いっしょに考えたり、うまく言えないことを代わりにつぶやいてくれたり。
ときどき、にゃぶが言うひとことに、わたしのほうがハッとさせられることもあります。



にゃぶりの詳しいプロフィールはこちら:
👉 にゃぶりのプロフィール
おわりに
このブログは、誰かを糾弾するためではなく、問いを共有するために書いています。海と社会と未来をつなぐ対話の場として、サメという存在が、きっと一役買ってくれるはずです。
ここまで読んでくれたあなたが、次の問いの担い手になりますように。