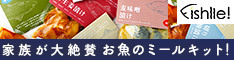にゃぶね、今日ガブッと読んだのは──
McMillanさんたちの論文「Do some tiger sharks prefer beaches? Insights for shark management from a broad-scale comparative tracking study」にゃ!
これは、オーストラリア・グレートバリアリーフ海洋公園で行われた、タグ付けしたイタチザメの再放流後の行動追跡研究にゃ。
Reinoとこの研究についてサメトークしたことを、にゃぶのヒレ日記に残すにゃ!

サメとヒトのすれちがいが増えてるにゃ
沿岸の人口やレクリエーション利用がどんどん増えて、ヒトとサメの行動が重なる場面が増えてるにゃ。
イタチザメ(Galeocerdo cuvier)は、世界のサメ咬傷事故でよく名前が挙がるけど、その存在が「危ないもの」と決めつけられる前に、まず海での行動パターンを知る必要があるにゃ。
この研究では、タグ付けして再放流したイタチザメ51匹と、それ以外のエリアでタグ付けされた82匹のサメを追跡比較して、「ビーチ周辺にまた来るかどうか」を調べたにゃ。
短時間の訪問だけど、そこに意味があるにゃ
結果としては、再放流されたサメの43.1%が、ビーチ付近に姿を見せたにゃ。
でもその大半は30分以内の短時間で、ほとんどが夜間の通過だったにゃ。
つまり「戻ってきた」っていうより、「行動範囲の一部をまた泳いだ」って感じに近いにゃ。
反対に、遠くでタグ付けされたサメがビーチに来たのはたった6.1%。
この差はあるけど、それを「危険」とラベリングする前に、サメの動きを「行動圏」という視点で見直す必要があるにゃ。
研究者にゃぶのヒレ解説
「1回そこを通った」=「そこに執着している」ではないにゃ。
海の道は、にゃぶたちが思うよりもっと広くて偶然に満ちてるにゃ。
サメの行動圏とヒトの境界線は違うにゃ
「ビーチに戻ってきた」という表現は、ヒトの視点での線引きにすぎないにゃ。
サメにとっては、そこがビーチなのか外洋なのかなんて、関係ないにゃ。
にゃぶ的には、この研究は「再放流後のサメの行動が予測できるかどうか」よりも、「ヒトとサメの共存のためにどういう理解が必要か」を示してくれてると思ったにゃ。

🧮 にゃぶのサメ関数オペレーションズ・リサーチ[空間認知の効用型]
にゃぶのORヒレを動かすにゃ!
今回の研究でにゃぶがいちばん気になったのは、「戻ってきた」という言葉が生むヒレずれにゃ。
にゃぶ、オペレーションズ・リサーチの考え方で、「サメの空間行動に対するヒトの受け止め方」を数式にしてみたにゃ。
ここでの U は「サメの空間行動がもたらす社会的安心感の効用」にゃ。
にゃぶ思うにゃ、「戻ってきた」というニュースはインパクトがあるけど、
それが「また来るかもしれない不安」を先回りして広げてしまうことがあるにゃ。
この効用関数で大事なのは、実際の行動(短時間の通過)と、ヒトの想像の間にあるギャップにゃ。
そのギャップを埋めるには、サメの行動圏に対する認知のチューニングが必要にゃ。
科学的知見が伝わらないままだと、不安の方が先に泳ぎ出しちゃうにゃ。

※「効用関数」は、状況の理解や安心感を数で整理して考える数理の道具にゃ!
「科学がどうだったか」よりも、「どう受け止められたか」によって、ヒトの安心が上下しちゃうにゃ。
再訪率が高くなくても、納得度が低ければ、不安コストが膨らんじゃうにゃ。
にゃぶ思うにゃ、この構造を整理することが、共存の第一歩にゃ。
サメの行動とヒトの受け取りにズレがあるとき、保全はどう伝えるべきか
にゃぶ、この研究から感じたいちばんの問いは──
「同じ海を、サメとヒトがちがう意味で見ている」ってことにゃ。
サメにとっては「通っただけ」のコースでも、ヒトにとっては「また来た」「戻ってきた」というニュースになっちゃうにゃ。
ここにあるのは、危険かどうかだけの問題じゃなくて、
誰が、どの視点から、どんな行動を意味づけするかのズレにゃ。
このズレがそのまま「タグ付けして再放流=危ないことをした」っていう印象にすり替わると、本来は科学に基づいて行われた保全活動が、社会の中で納得されない判断になってしまう危険があるにゃ。

サメとヒトが共存する未来へ、必要なのは「見え方のヒレ調整」
にゃぶが考えるにゃ。
これから大事になるのは、「サメの行動」と「ヒトの安心」のあいだにある
伝え方のヒレをていねいに調整していくことにゃ。
「サメはまた来るかもしれない」っていう可能性を、必要以上にあおるんじゃなくて──
🦈「どうして来たのか」
🦈「実際はどれくらいの時間・頻度なのか」
🦈「タグ付けして再放流する時点での科学的判断はどうだったのか」
こういう背景と意図の見える化こそが、共存の土台にゃ。
ルールをつくることも大事だけど、そのルールが「どうやって決まったか」「なぜそれが必要なのか」を、ヒトの言葉で届けることが、ほんとうのヒレ距離をつくるにゃ。
にゃぶのFAQ:読者の問いにヒレで答えるにゃ
Q1:サメが「戻った」って本当に悪いこと?

Q2:なんで科学的にタグ付けして再放流したのに批判されるの?

Q3:イタチザメの「再訪率」ってどうやって測ってるの?

Q4:タグ付けして再放流することががダメってこと?

Q5:この研究、他の場所でも通用する?

にゃぶりのガブっとコメント

博士帽メダル授与
ぬし、最後まで泳いでくれてありがとうにゃ! 今日のヒレメダルは「意味のずれを見つめる観察力賞」✨
論文データ
著者:Wohak et al. 掲載誌:Biological Conservation DOI:https://doi.org/10.1016/j.biocon.2023.110227
ヒレエンド

にゃぶ、また新しい潮目で会えるの楽しみにしてるにゃ🐟💙