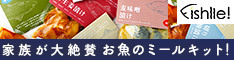にゃぶね、あのイスラエル・ハデラのニュースを見たとき、ヒレがピクッと動いたにゃ。
「サメが人を襲った」って言葉ばかり流れるけど、本当に聞くべき声は違うにゃ。
海の底で、サメたちはただ自分の「居場所」にいただけ。
でもそこに、ヒトのカメラと餌と興奮が押し寄せていたにゃ。

そのときの違和感が、後に研究として波に乗ったにゃ。
今日は、「Protecting sharks by protecting places」(Zemah-Shamir, 2026)から、「場所を守る」ってどういうことかを考えるにゃ。
背景:サメとヒトの距離が縮まりすぎた海
ハデラはイスラエルの発電所前に広がる港町。
冬になると、温排水(発電所のあたたかい水)に引き寄せられたサメたちが群れをつくるにゃ。
その姿を見ようと、ダイバーや観光客が毎年集まる人気スポットになっていたにゃ。
でも、2025年春——1人の命が奪われたサメ事故が起きたにゃ。
「なぜ起きたのか?」を考える前に、
まず「どこで」「どんなふうに」ヒトとサメが出会っていたのかを見つめる必要があるにゃ。
研究者にゃぶのヒレ解説
発電所の温排水(おんはいすい)とは、発電時に使った海水を少し温めた状態で海に戻すことにゃ。冬の冷たい海ではこの場所が「あたたかいオアシス」になって、サメや魚たちが集まりやすくなるにゃ。

論拠ヒレ:研究が示した「サメとヒトの交差点」
2026年の研究(Zemah-Shamir)によると、
サメ事故の背景には「サメが変わった」のではなく、「ヒトの行動が変わった」ことがあるにゃ。
調査チームはドローン映像・SNS投稿・観光者データを使って分析したにゃ。結果はこうにゃ👇
- サメ観察エリアには春だけで約4,500人が訪れていたにゃ。
- 餌付け、接触、水中撮影などの行動が常態化していたにゃ。
- 2025年4月、ドタブカ(Dusky shark)が人に反応して事故を起こしたにゃ。
- 原因は「誤認刺激」+「餌付け習慣」+「混雑」にゃ。

🧮 にゃぶのサメ関数オペレーションズ・リサーチ[空間行動型]
にゃぶのORヒレを動かすにゃ!
オペレーションズ・リサーチの考え方で、「サメとヒトの距離の最適化」を数式化してみたにゃ。
ここでの U は「海の安心と満足のバランス」を表す効用関数にゃ。距離が近すぎるとリスクが上がるけど、遠すぎると「理解の波」が届かないにゃ。「無関心コスト」は、見て見ぬふりをしたときに失われる未来の価値を指すにゃ。
にゃぶ思うにゃ、保全って「近づかないこと」じゃなくて、「適切に寄り添うこと」なんだにゃ。
ルールはそのための「目安のヒレ距離」にすぎないにゃ。

にゃぶの考察:保全とは「種」じゃなく「空間」を守ること
にゃぶはこの研究を読んで、ひとつの問いにぶつかったにゃ。
「サメの保全って、「サメそのもの」を守ることなのか?」
違うにゃ。
本当に守るべきは、「サメとヒトが出会う場所」——交わりの空間にゃ。

これからの波:行動を変えるための「空間ルール」
論文では、次のような提案がされていたにゃ👇
- 季節ごとの立入制限(サメの集まり期を考慮)
- 教育キャンペーン(観光者・地元住民への啓発)
- ゾーニング制度(観察・釣り・保護のエリア分け)
- 行動ガイドライン(餌付け・接触の禁止)
これをにゃぶ的に言い換えると、
「サメの安全距離を、ルールじゃなく「共感」でつくる」ってことにゃ。

にゃぶのFAQ:読者の問いにヒレで答える
Q1:この研究、結局なにが新しいの?

Q2:イスラエルのハデラってどんな場所にゃ?

Q3:サメ事故はサメのせい?

Q4:どうすればサメ事故を防げるにゃ?

Q5:世界にも似た場所ある?

にゃぶりのガブっとコメント:ヒトの足跡が、海の温度を変えるにゃ
にゃぶ、この研究を読んで思ったにゃ。
「サメに近づく」んじゃなく、「サメが安心できる空間をつくる」方がずっと優しいにゃ。
保全は、サメを遠ざけることじゃない。
ヒトが、サメとの「適切な距離」を覚えること。

論文データ
著者:Shiri Zemah-Shamir 掲載誌:Journal for Nature Conservation, Vol. 89 (2026) DOI:[https://doi.org/10.1016/j.jnc.2025.127117](https://doi.org/10.1016/j.jnc.2025.127117)

2025年4月海外のサメ事故の真相🦈なぜ起きた?
イスラエルのハデラで起きた #サメ事故 についての解説🦈
サメは基本的には人を襲う生きものではないけど...その行動は予想不可能🦈
わたしが個人的に思うこととしては、この海にくる人々がサメたちにストレスをかけすぎていたんじゃないかな。その結果として運悪く、事故に巻き込まれた人がいたというのはやるせない。