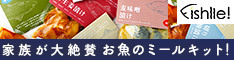海の食物連鎖の頂点に立つサメ、と聞くと、「ジョーズ」みたいな恐ろしいサメを想像する方も多いかもしれません。でも、実はサメよりも恐ろしいのは「人間」。
インターナショナルシャークアタックファイル「ISAF」によると、2024年にサメによって命を落とした人間は4人。過去5年間の平均は、年間6人。
一方で、私たち人間は毎年約1億匹ものサメの命を奪っています。(Davis et al. 2013)
このブログでは、サメのヒレだけを取って捨てる「シャークフィニング」という漁法、フカヒレにまつわる倫理の問題、そして本当に持続可能なサメ漁とは何かについて考えます。
シャークフィニングとは
まず、はじめにサメのヒレだけ取るシャークフィニングの問題について解説します。
シャークフィニングとは何か
※残酷なシーンが含まれているためご注意ください。
シャークフィニング(shark finning)とは、生きたサメから背ビレ・胸ビレ・尾ビレなどを切り落とし、そのまま海に廃棄することです。
フカヒレを取った後サメを海に捨てる
※残酷なシーンが含まれているためご注意ください。

サメのヒレだけ取るシャークフィニングの残酷さは、フカヒレ目当てにサメのヒレを取った後、サメを生きたまま海に捨てることです。
ヒレのないサメは当然泳ぐことはできません。呼吸もできず、海底に沈んで命を落とします。
また、切り取られたヒレが再生することはありません。
そのまま海底に沈み、溺れて死んでしまいます。

なぜシャークフィニングを行うのか
サメのヒレはフカヒレとして高価ですが、他の部位についてはマグロやカツオなどと比べて商業価値が低い魚です。また、サメは大型なため漁船で漁獲物をしまっておく魚倉(ぎょそう、魚艙)のスペースを確保するにも一苦労。European Elasmobranch Association(EEA)の資料によると、サメのヒレの重さは平均して体重の2%です。
つまり、商業価値が低いサメを船に積むのは邪魔、「ヒレだけ取る」ほうが効率がいいということになります。
シャークフィニングを加速するIUU漁業
この行為が繰り返される背景には、「IUU漁業(違法・無報告・無規制漁業)」の問題もあります。IUU漁業とは、強制労働や違法な漁法、乱獲、そして水産資源を守るための国際的なルールを無視して行われる漁業のことを指します。サメに限らず、ナマコやタツノオトシゴなど、海の絶滅危惧種の生きものたちがIUUの影響を受けています。
サメのヒレだけを切って持ち帰るシャークフィニングは「軽くて高価な部位だけを狙う」漁法です。この方法なら、サメを丸ごと積むよりもはるかに効率的に、多くのヒレを漁船に積み込むことができます。
つまり、IUUのような規制を無視した漁業にとってシャークフィニングは「小さなスペースで大きな利益を生む効率のよい密漁」になってしまうのです。
そのため、IUU漁業はシャークフィニングの温床にもなっており、わたしたちが気づかないところで、いまこの瞬間もサメの命が静かに奪われ続けています。
残酷なシャークフィニングへの規制
この残酷すぎるシャークフィニングやフカヒレについては、漁業管理機関や国・地域によっては規制・禁止されています。2016年には、サメの多さが世界一のガラパゴスでフカヒレ密漁が増加したため、周辺海域に新たに禁漁区が設けられました(National Geographic)。
また、太平洋をはじめとする国際漁業管理機関では、遠洋マグロ漁業におけるシャークフィニングを禁止しています。それでもなお、市場に流通するヒレの量と、報告されるサメ漁獲量との間には大きな差があります。これはつまり、ルールがあるにもかかわらず、それをすり抜ける構造が今も存在しているということです。
規制は重要です。
けれど、規制があることと、それが守られていることは別の話。監視の目が届かない公海やIUU漁業では、ルールを破る違法な漁が今も繰り返されています。
つまり、サメの命を本当に守るには、ルールを整えるだけでなく、それを実際に機能させる「しくみ」と「監視の目」が必要なのです。
シャークフィニングの今
実際、日本や中国の遠洋マグロ漁船では、禁止されているはずのシャークフィニングが行われていた事例が報告されています。
2018年、日本のマグロ漁船で働いていた乗務員が、約1年間でサメ約300匹をフカヒレ目的で密漁していたとされる事件。「生きたサメからヒレを切り、体を投げ捨てた。船長の指示だった」と証言しています(参考記事:「日本のマグロ漁船サメ密猟の疑い インドネシア人漁師供述の真相は?」)。
また2021年には、中国の遠洋マグロ漁船において、大規模なシャークフィニングが行われていたことが、英国の環境団体と共同通信による調査で明らかになりました。
調査では、インドネシア人の元乗務員約70名の証言と、船上で撮影された写真が提供され、2017年〜2020年にかけて複数の漁船で、サメのヒレだけを切り取り、体を海に捨てるシャークフィニングが常態化していたと報告されています。
さらに、この漁船群は日本向けの冷凍運搬船と繋がっていた可能性があり、一部は日本の大手商社の子会社が運航していたとの指摘もあります(参考記事:「共同通信「Japan likely imports fish from Chinese ships flagged for illegal acts」」)。
つまり、日本の市場にも、こうした違法・非人道的な漁業による水産物が「知らぬ間に流通している可能性」があるのです。
・2025年までのシャークフィニングの詳細な事例は以下の記事にまとめています:
【2025年】フカヒレ漁の一覧|サメ密漁とシャークフィニングの今
フカヒレの需要と文化背景
※残酷なシーンが含まれているためご注意ください。
シャークフィニングが問題視されるのは、サメの扱いが残酷ということだけではありません。
もうひとつの大きな理由──それは、「フカヒレ」に対する需要が世界中のサメの個体数に深刻な影響を与えているからです。
推定では、毎年1億匹以上のサメが人間の手によって命を落としています(Worm et al.2013)。
その多くは、フカヒレを目的とした漁によるものです。
では、なぜこれほどまでにフカヒレが求められるのでしょうか?
その背景には、食文化、伝統、そして「豊かさ」を象徴する食卓の物語が絡み合っています──。
フカヒレの需要
フカヒレスープは、東アジアや東南アジアを中心に高級料理として長く親しまれてきました。
中国では「四大海味(なまこ・あわび・魚の浮袋・フカヒレ)」のひとつとして扱われ、伝統的な宴席や祝宴で「豊かさと敬意の象徴」として重宝されています。
こうした背景のもと、世界のフカヒレ消費量の約90%を中国が占め、特に香港は世界のフカヒレ取引の約50%を担う一大流通拠点となっています(Ref.3)。
- フカヒレ輸入量:世界1位=香港(8万3210トン)、2位=マレーシア(3万3894トン)
- フカヒレ輸出量:1位=タイ(4万7208トン)、2位=香港(4万1877トン)【Ref.5】
その結果、フカヒレの需要はサメの個体数に深刻な影響を与えています。ある研究によれば、年間で少なくとも1億匹以上のサメが殺されているとされ、これは1日あたり約24万7000匹、1時間あたりおよそ1万1000匹という計算になります(Ref.1)。。
その多くが、フカヒレスープを目的としたヒレの取引に結びついています。この「高級食材」という価値が、結果的にサメたちにとっては命を脅かす圧力になっているということです。




香港とフカヒレ
世界のフカヒレ取引の約50%を担う香港では、フカヒレスープが結婚披露宴の定番メニューのひとつとされています。参列者が「最も楽しみ」「披露宴でフカヒレを出さないのは失礼」と語ることもあるこの一品ですが、近年ではフカヒレを目的としたサメの乱獲が国際的に問題視されるようになり、披露宴でフカヒレスープを出さない若者カップルも増えています(Ref.5)。
「フカヒレなし披露宴」は、海洋生態系の保護に貢献できるだけでなく、コスト削減の面でも若者たちの支持を集めています。2015年の調査では、香港の披露宴でフカヒレが提供された割合は6割にとどまりました。高級ホテル「ザ・ペニンシュラ」を展開する香港上海大酒店は2012年からフカヒレ料理の提供を停止し、キャセイパシフィック航空も2015年6月にフカヒレ製品の輸送を禁止しました。(Ref.5)
シンガポールとフカヒレ
実はシンガポール料理にもフカヒレが使われることは少なくありません。
しかし、サメの乱獲が問題視されるなか、近年は消費を控える動きが広がっています。
たとえば2014年には、シンガポールを代表する観光ホテル「マリーナベイ・サンズ」が敷地内での提供を中止。
さらに、シンガポール航空の貨物部門もフカヒレ製品の取り扱いを停止しました。
また、WWFが2016年にシンガポールで実施した調査では、82%の消費者が「フカヒレを1年以上食べていない」と回答しています。(Ref.4)
フカヒレと文化
フカヒレの問題が複雑なのは、単に食材としての好みではなく、「文化」の一部として受け止められている点にあります。たとえば、中国ではフカヒレが特別なごちそうとして扱われてきた歴史があり、その起源は400年以上前、明の皇帝にまでさかのぼります。
このような背景を持つフカヒレをめぐって、「やめてください」と伝えることは、単なる食習慣の変更を求める以上に繊細な意味を持ちます。特に「文化だから」という言葉が出てくると、それはしばしば「批判の及ばない聖域」のように扱われてしまうことがあります。
文化とは本来、変化し、対話の中で育まれていくものです。けれども、「文化ですから」と言われると、それ以上踏み込んではいけないような空気が生まれやすい。その結果、たとえ科学的な根拠に基づいた批判であっても、どこか「失礼なことをしているのでは」という感覚にとらわれてしまうこともあります。
たとえば、フカヒレには滋養強壮や不老不死の効果があると信じられてきましたが、現代の科学的知見から見れば、それが事実ではないことは明らかです。しかし、「文化」とセットで語られると、こうした信仰や伝統に異を唱えること自体が「悪いこと」のように見えてしまうのです。そういう意味で、「文化」という言葉は、時に「対話を拒むための盾」として使われてしまう危うさをはらんでいます。もちろん、文化への敬意はとても大切ですが、それと同時に、変化を恐れず、環境や倫理の観点から再考する勇気もまた必要です。
参考:石井 敦、真田 康弘『クジラコンプレックス 捕鯨裁判の勝者はだれか』、東京書籍、2015年。

日本のサメやフカヒレ文化
日本でサメはフカヒレ、地方料理での珍味、珍味かまぼこなどの練り物や鮫皮おろしとして活用されており、サメを食べたりすることは文化のひとつといわれています(わたしはサメを食べないので日本といってしまうと主語が大きすぎるかもしれませんが)。
最近では、水族館でのフードコートでもサメ肉を使ったナゲットやカレーなどを食べる場所もあるので、サメを食べたことがある人も増えてきているかもしれません。
また、サメを使った料理、レシピ、実食レビューなどをSNSなどで目にすることも多いのではないでしょうか。
文化としてサメを食べていく日本や中国においては、特にフカヒレ取引に関する規制の強化や、資源量の把握と管理を前提とした「持続可能なサメ漁のあり方」が、これからますます問われていくのではないでしょうか。
サメ漁と保護の現実
サメを守る動きが世界的に広がる一方で、その実情は決して単純ではありません。
サメの保護とフカヒレ漁の規制
サメが生態系や人間社会にとって重要な存在であるという認識が進み、国際的な保護の動きが加速しています。
たとえば2013年、ワシントン条約(CITES:絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)では、新たに5種のサメが付属書IIに登録され、無規制な取引によって絶滅の危機に陥ることを防ぐ措置が取られました。
さらに、1994年以降、22の国がフカヒレ漁に対する何らかの規制を導入しており、中国でも2012年に公式行事でのフカヒレスープ提供が禁止されるなど、文化的な見直しの動きが一部で見られるようになりました。
しかし、ホテルや飲食業界の一部で提供を中止する動きがあったものの、「フカヒレ=高級食材」という需要の構造そのものは、ほとんど変わっていません。
サメの個体数は減少し続けている
2025年現在、IUCNレッドリストでは、世界のサメ類557種のうち、およそ30%にあたる168種が絶滅危惧種と評価されています。その原因の多くが人間の漁業活動(IUUなどのフカヒレ漁、混獲、乱獲)や海洋汚染にあります。アカシュモクザメととシロシュモクザメのうち130万匹から270万匹がフカヒレの取引で毎年犠牲になっている考えられています。(Ref.1)。
サメは他の魚類に比べて、寿命が長く、成長が遅く、一度に生む子どもの数も限られています。そのため、一度個体数が減ってしまうと、自然回復には非常に長い時間がかかってしまうのです。たとえば、水揚げ量が多いヨシキリザメの寿命は約20年、アオザメに至っては30年近く。資源回復には通常、その魚が成熟して再生産を繰り返すのに必要な時間────つまり寿命に匹敵する、あるいはそれ以上の期間が必要とされる場合もあります。
サメに限らず、過剰に獲られた魚は、生物学的に回復が困難になります。どのような対策を講じたとしても、すべての魚種資源を短期間で再構築することはできません。
※一部の研究では、回復には寿命に相当する、あるいはそれ以上の期間が必要とされると示唆されています。
絶滅危惧種のサメもフカヒレに
サメのヒレの多くはアジア市場に出回っています。
研究者と環境保護団体のチームがアメリカ国内のレストランでフカヒレスープを集めました。
その目的はフカヒレスープに含まれるサメの遺伝子を調べることです。
アメリカの14都市から集められた51のフカヒレスープを調べたところ、その結果は驚くようなものとなってしまいました。
DNA検査の結果、8種類のサメが確認され、その中には絶滅危惧種のサメも含まれていたのです。

葛西臨海水族園のアカシュモクザメ。2021年6月に撮影。
ボストンで採取されたフカヒレスープには、アカシュモクザメが含まれていました。
アカシュモクザメは、国際自然保護連合の絶滅危惧種のレッドリストで絶滅危惧種とされています。(Ref.2)
また、フカヒレ貿易の中心地である香港のフカヒレ取引では特定されたサメの3分の1以上の種が絶滅の危機に瀕していることがわかっています。(Ref.3)
フカヒレの需要は世界中のサメたちが直面している最大の脅威のひとつです。
現在、香港がフカヒレ貿易の拠点となっていますが、その貿易に貢献している国は約80数カ国にのぼります。(Ref.2)

漁業では特定の魚だけ避けるということができません。
そうなると当然、絶滅危惧種のサメも捕まってしまいます。
サメの保護活動や環境問題への意識が高いイギリスですら、フィッシュ&チップスに絶滅危惧種のサメの肉が使われていたことがわかりました。そのようなことが起きてしまう理由は、混獲してしまったサメについては販売することに問題がないからです。
魚を獲ればサメが獲れます。
混獲を避けることはできません。
そのため、混獲などで死なせてしまった絶滅危惧種のサメについては食べるなどして活用することはせめてもの報いです。
この状況下で、サメを守るにはオーシャンDNAによるサメの分布の調査、海洋保護区の設置などが考えられます。
※オーシャンDNA(海水中のDNAを解析し海洋生物群の分布や回遊ルートなどがわかる生物海図の作成に利用できることが期待されている。東大×SDGs: 先端知からみえてくる未来のカタチ)
サメの保全と社会活動は切り離せないものであり、どちらにも配慮が必要です。
海洋保護区の設置は簡単なことではないかもしれませんが、チリのように持続的な漁業のために小さな保護区を随所に作るというやり方がもっと広まれば、漁業で生計を立てている人の生活もサメたちも守ることができるのではないでしょうか。(参考:海の保全生態学)
日本とフカヒレ
気仙沼のフカヒレ

日本の気仙沼のサメ漁の水揚げの8割を占めるヨシキリザメは、マグロと一緒に漁獲されます。
シャークフィニングは行わず、サメのひれをつけたままで港に水揚げします。その後、サメの加工会社で、身・皮・骨・ヒレなどまるごと加工されていきます。気仙沼ではサメの総合活用が行われており、不要な部分を海中に投棄するようなシャークフィニングとは対照的です。
資源を無駄なく使おうという気仙沼のサメ総合活用は日本のもったいない精神を反映したひとつのかたちかもしれません。
しかしながら、ヨシキリザメのような絶滅危惧種ではないサメも個体数に限りがあります。そのため、資源管理をしつつ、サメの総合活用をするということが大切でしょう。
サメを保全する方法は?
人間が魚を食べる限り、サメの混獲を避けるということは不可能です。
では、どのようにしてサメたちと付き合っていけばいいのでしょうか。
持続的なサメ漁業や保全の方法について考えてみました。
持続可能な方法で漁獲された「サステナブル・シーフード」を目指す
わたしたちが食べている魚介類の未来を守るためには、「どのように、どこで、どれだけ獲るか」がとても重要です。こうした観点から漁業を見直し、資源の枯渇を防ごうとする取り組みが「サステナブル・シーフード(持続可能な水産物)」です。
具体的には、漁獲量の適切な管理や、混獲を減らすための漁具の工夫、そして漁業の持続可能性を第三者が審査・認証する「MSC認証(海のエコラベル)」の活用などが挙げられます。
たとえば、ヨシキリザメの水揚げ量が全国一位を誇る気仙沼では、2021年に「ヨシキリザメ・メカジキはえ縄漁業改善プロジェクト(FIP)」がスタートしました。この取り組みでは、以下の目標が掲げられています。
- 気仙沼の漁業が乱獲を行っていないことを示すこと
- シャークフィニング(ヒレだけを切り取って捨てる行為)をしていないことを明らかにすること
- こうした実践を証明し、2026年までにMSC認証の取得を目指すこと
そのために、漁獲情報の精度向上や、漁業が生態系に与える影響の評価方法の改善など、課題解決に取り組んでいます。MSC認証では、資源の持続性、生態系への配慮、管理体制の確かさが求められるため、それらを総合的に満たす必要があります。
このように、MSC認証の取得を目指すことは、漁業者の暮らしを守りつつ、サメを含む海の資源を適切に管理する道筋となります。経済と保全を両立させる一つのモデルともいえるでしょう。(参考記事「〈変わる海・漁業転換〉サメ無駄なく活用 持続可能産業へ世界発信」、「日本初! MSC認証取得を目指して ヨシキリザメ・メカジキはえ縄漁業改善プロジェクト(FIP)を開始[シーフードレガシー]」)
私たち消費者も、サステナブル・シーフードの流れを支える当事者です。MSCの青いラベルがついた水産物を選ぶことが、持続可能な漁業を後押しする行動になります。漁業者だけに責任を求めるのではなく、「どんな魚を選ぶか」という毎日の小さな選択を通じて、私たち自身も未来の海づくりに参加していくことが求められています。
フカヒレよりも経済効果が大きいエコツーリズム
フカヒレよりも大きな経済効果を上げる方法はサメをいかしたエコツーリズムです。
2016年に米国が輸出したフカヒレの収益は100万ドル以下でしたが、フロリダ州でのサメ関連のダイビングだけで2億2100万ドル以上の収益を上げ、同年に3700人以上の雇用を促進しました。つまり、フロリダ州のサメ観光による収益は、米国の全フカヒレ輸出の200倍以上にもなります。(Ref.3)
このようにサメを観光にいかしたエコツーリズムのような非消費的利用の動きが広まっていくとサメの保全につながっていくかもしれません。また、経済効果があるということは雇用を生み出すのでサメの保全だけではなく、人間社会も守ることができます。
フカヒレになってしまったらサメの経済効果は一回きりですが、エコツーリズムなら何回でも経済効果をもたらしてくれます。




人工フカヒレを活用する
人工フカヒレとは、フカヒレ漁のためにサメが乱獲されることを防ぐために、ゼラチンや海藻由来成分などを原料に開発された商品です。
食感と透明感はまるでフカヒレというゼラチン加工食品の人工フカヒレ。
ZIPが行なった調査でも、本物と比較しても見た目に目立った違いはなく、本物のフカヒレスープと食べ比べてみてもハッキリとした違いはわからないとのことでした。
高級食材フカヒレと人工フカヒレ、その違いって何?
高級中華料理店の調理長さんに伺うと、フカヒレ自体はほぼ無味無臭とのこと。
味と香りでは、人工フカヒレとの判別できない。
引用:ZIP
日本と欧米のサメ保護論について思うこと
わたし個人の立場としては、欧米のサメ保護論とそれに対する日本の反論の両方を批判的に捉え、自分なりのサメの保護・保全論について試行錯誤をしています。
気仙沼のサメ漁については持続可能なサメ漁に取り組んでいると思うのですが、国外でのサメ漁については気になる点があります。
日本は海外のサメ保護論に対して、「正確な情報提供に努めつつ、機会を捉えて反論する」と主張しています。ところが、日本のサメ漁への取り組みについて、じっくり調べていくと疑問を感じる部分があるのも事実。
たとえば、サメ漁やフカヒレを肯定する日本側の資料や主張では、サメは繁殖率が低く乱獲に弱いことには触れられていません。サメが絶滅危機ということについて、「外国の環境団体がクジラのときと同じように騒いでいるだけ」という批判が日本側にありますが、そういう問題ではありません。確かに、一部の環境団体はセンセーショナルな情報発信を行い、誤解を招いていることは事実です。
しかしながら、サメが絶滅危機にあることに対して警鐘を鳴らしているのは環境団体ではなく研究者です。
ネイチャー誌に掲載された論文によると、1970年以降、相対的な漁獲圧が18倍に増加したため、世界のサメ・エイ資源量は71%減少ということが明らかになりました(Pacoureau et al.2021)。
そのような状況でサメの個体数減少の問題には触れずに、「ネズミザメやヨシキリザメの資源量は安定しています!サメを食べましょう!」と主張するのは違うのではないでしょうか。
また、サメと水銀の問題についても外国の環境団体の言いがかりのように扱われてしまいますが、サメと水銀については厚生労働省が「魚介類に含まれる水銀について」で妊婦、子ども、一般、イルカ・クジラの多食者などに向けて、「食物連鎖の上位にある、サメやカジキなどの大型魚や、一部のハクジラのほか、キンメダイのような深海魚等は、比較的多くのメチル水銀を含んでいます。」と言及しています。
サメを有効活用して持続的に食べていくことを主張するからこそ、
- 不都合な情報を明らかにしつつ、絶滅の危機に陥っている種もいるサメをどう持続的に活用していくか→保全
- 混獲したサメを廃棄しないためにサメ食を推進する→利用
という保全と利用の両面からアプローチするべきと思います。
日本人だから日本の言い分をすべて信じる、サメが好きだから欧米のサメ保護論をすべて信じるというのはどちらも間違っていると思います。わたしはサメを食べたくないのでそこだけ切り取ると欧米のサメ保護論寄りかもしれません。
しかしながら、双方の主張をすべてを鵜呑みにせず精査し、疑問をもちながら、サメの保護・保全について考えていくことこそが大切だと考えています。
おわりに
![]()
現在、サメやエイ、ギンザメを含む「軟骨魚類」のうち絶滅危惧種と認定されているのは167種のサメと114種のエイと1種類のギンザメです。
これは「軟骨魚類」全体のおよそ4分の1にあたり、ホホジロザメやジンベエザメやシュモクザメの仲間も含まれています。
今のところ脅威にされされていないと考えられる種は、全体の23%しかいません。
ここまで述べたようにフカヒレ問題は文化や産業と結びついている面もあるので、みんなでやめましょうという簡単な話ではありません。
また、シャークフィニングをせずにすべてを活用し、資源管理も行なっているような持続可能なサメ漁については批判すべきではないと考えています(もちろん、わたしはサメ愛好家なのでわたし個人の感情論だけで意見するならばサメ漁をして欲しくはありませんが、これはあくまで「感情」です)。
ただし、シャークフィニングでヒレ切りをするのも、サメのすべてを活用することも、サメが死んでしまうことには変わりはありません。
そのため、日本が正しい、環境団体が正しいということを裁くのではなく、どうすればサメの個体数を維持できるのか、個体数が激減しているヨゴレの個体数を元に戻せるのかなど、サメをはじめとした海洋生物を主役とした議論を進めていくことが必要だと思います。
正直、日本ではワシントン条約や環境団体への反発、不都合な部分には触れることなくサメの活用だけをアピールしているケースが多く目につきます。サメがいなくなってしまっては、文化も活用もできなくなってしまいます。サメの有効活用もサメがいてこそできることなのです。
ワシントン条約や環境団体への反発ではなく、サメ食やフカヒレ文化、サメに関連した水産業を守ることを目的に、どうすればサメを保全できるのが、持続可能な漁業ができるのかを考えることこそが急務だと思います。
17の「持続可能な開発目標(SDGs)」のうち、SDGsの目標14「海の豊かさを守ろう」に掲げられているように、わたしたちは海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用していくことに向き合うべきなのではないでしょうか。
自分一人が大きなことを変えることができるわけではありませんが、関心を持つこと、知ること、自分なりに調査して考えてみること。
このような些細な行動でも、それを世界中の人が行うことにより、ものごとが大きく変化していくということはあると思います。
「自分には何ができるんだろう?」
ぜひ、考えてみてください。


余談ですが、子どもの頃「サメ好きでしょ?今日の夕食はサメよ!」といわれたときに「好きってそういうことじゃない」と思って、テンションが下がったことを思い出しました。
(2)Learning English, “Efforts to End Shark Finning Make Progress” 2021年2月26日に閲覧
(3)Oceana, “TELL CONGRESS: BAN THE TRADE OF SHARK FINS IN THE U.S.” 2021年2月26日に閲覧
(4)産経新聞電子版(2017.6.13 05:00)『シンガポール、フカヒレ貿易規模高止まり 国内では消費抑制の動き』、2021年6月28日に閲覧
(5)産経新聞電子版(2017.7.24 05:00)『披露宴のフカヒレ姿消す? 香港、サメ乱獲で若者は自制』、2021年6月28日に閲覧
"Global catches, exploitation rates, and rebuilding options for sharks",2013
サメの保護・保全についての関連ブログ
多くのサメが絶滅の危機に直面している原因とは?
サメといえば獰猛で恐ろしい海のハンターというイメージを持っている人も多いのではないでしょうか?ところが、世界の海に生息するサメの個体数はここ50年間で大きく減少しています。水族館でおなじみのシロワニやアカシュモクザメ、ジョーズで有名なホホジロザメなども実は絶滅危惧種なんです。 今回の動画では、多くのサメが絶滅の危機に直面している原因についてお話しします。【資格】SDGs検定合格講座(オンライン講座)
かわいいサメと暮らしたい人におすすめ

AQUA ぬいぐるみ マリン ガブッと サメ 00280146